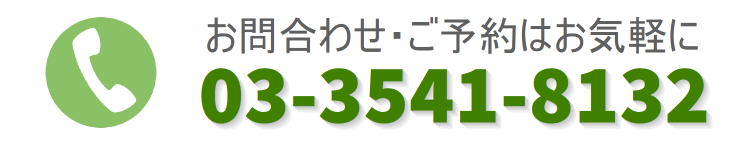歯周病治療とは🤔⁇
日毎に寒さが増し、銀座の街では黄色い銀杏の葉が舞う季節となりました。
大学医局員を退職して以来、毎年秋になると非常勤講師として母校東京歯科大学の歯周病学実習に参加しており、今年もその季節がやってきました。
この実習は、臨床実習前に4年生の授業として行われるもので、マネキンの並んだ実習室にて歯周病治療の流れを学んでいきます。歯周病の状態を再現した模型を使って治療手技を身につけるのはもちろん、学生同士で歯科医師役や患者さん役となって、病状や治療について説明しあうこともあります。

実習で使用する模型
(この模型を使用しブラッシング、歯石の除去、歯茎の手術といった手技の練習を行います)
ところで『歯周病』というのは、う蝕(虫歯)と並ぶ歯科における2大疾患の1つで、よく知られている病気です。例えば歯ブラシや歯磨剤のテレビCMなどで、歯周病になると歯茎がブヨブヨになり、骨が溶けて歯がグラグラ、そしてしまいには抜け落ちてしまう…という説明を見聞きしたことがある方も多いのではないでしょうか。
おそらく、皆さん歯周病予防には歯磨きが大切であるということは理解していることと思います。
ところが毎日歯科診療にあたっていると、歯周病の治療法というのは意外と知られていないような印象を受けます。
歯周病治療の流れを簡単にまとめますと、次のようになります。
1.検査
2.診断
3.治療計画を立てる
4.歯周基本治療(ブラッシング指導・歯石取り・虫歯治療等)
5.歯周組織検査
6.歯周外科治療(歯周病が進行している部分の手術:必要な場合)
7.歯周組織検査
8.口腔機能回復治療(被せ物・義歯・インプラント・矯正)
9.メインテナンス
重症度にもよりますが、歯周病の治療というのはこのように幾つものステップを踏みながら進めていくため、一定の回数や期間で終わるものではありません。
また虫歯治療と異なり、患者さんの日々のブラッシングの出来具合によって治療効果が左右されてしまいます。ですから、磨き残しが多い場所があれば、繰り返し指導を行なわせていただくこともあります。少々煩わしいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、歯科医師や衛生士がブラッシング指導を行うのは、このためなのです。
一方で、汚れの付きにくい口腔内にするのは歯科医師の役目でもあります。
たとえば片山歯科医院では、詰め物や被せ物を入れる際、歯との適合を限りなく良くするための調整に時間をかけさせていただいております。歯と人工材料の境目がなだらかになればなるほど汚れが付きにくくなり、虫歯の再発を防ぐと同時に歯周病も予防することができるからです。
一度治療をしたら、その後は長く安定した状態を維持できるようにすることを目標に日々診療しております。
歯周病に罹患してしまっても、健康なお口を目指して一緒に治療していきましょう。