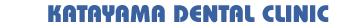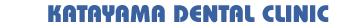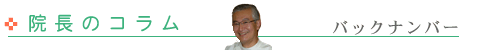|
ホームへ > 院長のコラム最新号へ
|
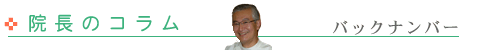
歯の色のお話 その3
梅雨が明けたのか未だなのか、とにかく蒸し暑くて参っています。いつもならこの時期に雷雨がやってきて、
埃を流して空気もきれいにしてくれるのに、今年はただただ蒸すばかりで閉口しています。
日本海側や長野県では、大雨による被害が相次いで心配です。くれぐれもお気をつけ下さい。
さて今月もまた、歯を白くする方法のお話の続きをしましょう。
先月は、歯を削らずに白くする方法のお話をしました。今月は、歯を削って白い材質のもので補う方法です。
歯を削るわけですから、設計や材質の選択には、より慎重な考慮が求められます。
そこで、いくつかの分類をして治療の選択肢をお話ししましょう。
先ず材質による分類では、白いセメント、レジン、硬質レジン、ハイブリッドセラミック、セラミックが今あるものです。
セラミック以外は、時間の経過と共に磨耗や傷によっての変色や、変質、が起きて表面の光沢がなくなってきます。
しかしそれぞれに加工のしやすさや、歯の削る量が少ないなどと言うメリットもあります。
私の場合は、白いセメントは、知覚過敏などの症状緩和の様子を見るための暫間充填物として、レジンは、治療中の歯の仮歯として使用しています。
後の3つは、本修復材料として症例によって使い分けをしています。
次に作り方による分類は、直接口腔内で修復する場合と型取りをして模型を作りその上で修復物を作る間接法があります。
私の場合は、比較的小さな範囲での修復には前者を用い、冠全体とか連結が必要なときには後者を選択します。
今度は、設計方法による分類をしましょう。
先ず単独の冠か、連結冠か、中間に歯の喪失している場所のブリッジかによる修復法の違いがあります。
次に、歯の削り方で、むし歯を除去して出来た穴につめるのか、歯の表面だけを削って修復物を貼り付けるのか、
冠全体を削って冠を被せるのかによる違いがあります。
さて私の場合は、ケースバイケースですが、最も多用している方法が、
プラチナとゴールドの合金を鋳造したフレームの上にポーセレンを焼き付ける所謂メタルボンドです。
最近では、このフレームも特殊なポーセレンで作りその上にポーセレンを焼き付けるという金属を使わない方法も取り入れています。
以前お話しした、薬剤による着色歯を白くする時には、その歯に何の異常も無い場合、表から見える部分だけを削って
その部分にポーセレンを焼いたものを貼り付けるポーセレンラミネートベニアと言う方法を用いる事もします。
今回まで歯を白くするお話をいろいろと申し上げましたが、私から特に申し上げたい事は、
どのような方法を選択しようとも天然歯に勝るものは未だ無いという事です。
歯の表面についたヤニや茶シブなどは、診療室にお出で下されば綺麗になります。
定期検診は、汚れた歯を綺麗にするためだけのものではありませんが、定期的に清掃することでエナメル質に出来たマイクロクラックなどに付く着色は、
中に染み込む前に取り除けますし、同時にフッ素塗布をすることで表面にバリアーを作る事も出来ます。
しかし、生まれつきあるいは年齢と共に着色が強く、人に歯を見せたくないなどの悩みをお持ちの方は、諦めないで下さい。
このような多種多様な選択肢が出て来たのは、ここ20年くらいの事です。従って、歯の削り方や材料の選択法などと共に次々新しい方法が考えられています。
私も、日々情報を受信しながらその都度その方に、最良にして最高の治療法を心がけてゆきたいと思っております。
皆さんが自然な美しい笑顔でいられるようにお手伝い出来れば私も幸せです。
このページの上へ↑
|
|
|